| <<前のページ | 次のページ>> |
| 2010年6月25日(金) |
| カトリックは、時代とともに進化する?! |
 |
 |
|
カトリックとは「普遍」という意味で、2000年の歴史があり、プロテスタントとは異なり、教皇を頂点として全世界同一の教義で、今日まで来ているとの印象がある。
しかし、それは看板だけであって、内容的には時代に合わせて変化しているというか、進化しているのだとの印象を強く持った。
今年度の司教総会が終わり、各委員会役員担当が交代したとのことで、一覧表が載った。その委員会を見ると、2、30年前には考えられなかったような名称がある。
新聞事業部、教会行政法制委員会などは、組織的な制度確立や、社会にPRしていくためには必要だろうと、誰でも納得する部署だろう。
諸宗教部門、エキュメニズム部門になると、以前とは様相が違っていることに気づく。私が子どもの頃の教会は「我こそ絶対」という感じで、他宗教やプロテスタントなどは「異端」だくらいの考え方だった記憶がある。葬式に行っても焼香もしてはいけないような口ぶりだったから。
正義と平和協議会、難民移住移動者委員会、部落差別人権委員会、『同和問題』にとりくむ宗教教団連帯会議、部落問題に取り組むキリスト教連帯会議、外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会、子どもと女性の権利擁護のためのデスク、HIV/AIDSデスクなどとなると、これがカトリックの機関かと目を疑う御仁も居られよう。
カトリックが「社会主義者に乗っ取られた」と考える信者もいるようだ。名称だけを見れば、確かに社会主義者が言っていることと同じに見える。ときによっては、社会主義者よりも過激な論調を展開することもある。
だからといって「カトリックは社会主義になった」とは言えないと感じている。
神の前で人間は平等であり、神によって人間の自由が保障されている。など、人権や自由の裏付けが神にあることが、根本的に違う。社会主義の場合は、主義だからその裏付けをなにに求めるのか知らないが、神という絶対的な裏付けを持つ教会だから、社会主義という主義だけよりも強いように感じる。
「すべてを神に委ねて、思い煩わず生きろ」が聖書の教えだからと、なにも社会的活動をしない信者が居るとしたら、彼らは信者としての立場を失うことになりそうな状況だ。
NPT会議に合わせて、長崎の大司教が米国を訪問した記事でも、それを感じる。
2000年の歴史のなかでは、こんな風に時代の状況を読んで、活動の範囲を変えてきたのだろう。だからこそ、2000年間続いてきたのだろう。もし、2000年前と同じことを言っていたら、信者は減り、社会的発信力も衰え、教会が消滅していただろう。
自分にとっての信仰だけにとどまっている信者は、これからの社会で生き残っていくことは難しいだろう。それに気づくことができるかどうかだが・・・
|
|
|
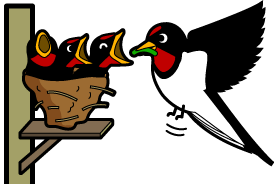 |
| 2010年6月24日(木) |
| やっぱりツバメの子どもだ |
|
夕方4時過ぎに出先から帰宅し、家に入る最後の角を曲がると、電線に黒っぽい小さな鳥が2羽止まっていた。「ツバメ?!」と思ったが、どうも尾のあたりがツバメ特有の「燕尾服」になっていないし、ツバメにしては小さすぎる。しかし、あの黒い形は確かにツバメに見える。視力にも自信がなくなったし、我が家の周りに、ツバメは今まで居なかったから、見間違いかなと思い、しばらく様子を見ていた。
角のお宅の方がガレージから出てきて「どうしたのですか」と聞く始末。3軒向こうのばあさんは、常日頃から怪しげな言動をしがちなのに、きょうはまた上を見上げたままじっとしている。さては空に怪しげな影などを見ているのではないのかと、疑っているような顔。「いえ。ツバメみたいなんですが、ちょっと違うようでもあるので、何の鳥かなと見ているんです」と弁解。「あらそうなんですか」と、興味なさそうに車で出かけてしまった。ツバメより自分の用事の方が大事と言わんばかりに。
なおも目をこらして見ていると、羽づくろいを始めた。「やっぱりツバメだ! あのしっぽは短いけど、確かに『燕尾服』だ」と、我が目はまだ確かなりと嬉しくなった。
「それにしても何で短いの? もしかしたら子どもとか・・・」との疑問でさらに見ていると、疑問は解決。推理は的中。
親と思われる大きさの「ツバメです」という姿をした鳥が飛んできて、何と電線の鳥にエサを与えたのだ。「なるほど! 巣立ったばかりで、どうにか電線までは飛んできたが、まだ自分でエサは取れないから、親にもらっているんだ」と、すべてを了解。
反対側からもう1羽飛んできて、2羽目にエサをやっていた。夫婦で子育て真っ最中のようだった。
4月頃に渡ってきて、今はもう、1回目の産卵での子どもが、巣立ちのときになったのだ。それにしても、何処に巣があるのだろう。見渡した範囲には巣らしいものはない。
7時近くなってコンビニに行った帰りに、二つ先の大通りにツバメを見つけたが、さっきのツバメかどうかは分からなかったし、大通りの何処かに巣がある様子もなかった。
4月頃から来ていたのだから、今までに気づく機会はあったと思うが、全く知らなかった。ごく近くに巣があるのではなく、いくらか離れた所に巣があって、きょうはたまたま親子で「遠出」をしたのかもしれない。
買い物の荷物が重かったので、親子が飛び去るまでは見ていられなかったから、何処に飛んでいったのかは分からない。
息子達が保育園に行っている頃は、もっと「街」になっている所に、ツバメが毎年来ていた。息子達に「ツバメがまた来たよ」と言いながら車を走らせたものだ。
あの時すでに「ここにツバメが来るのはいつまでかな。ひょっとしたら我が家の方に引っ越してくるかも」と思ったものだった。
今、それが現実になった。保育園時代の街からは、ツバメは全く姿を消してしまっている。我が家の周りには来ていなかったが、これから来るようになるかもしれない。
近くに田圃はないが、小さな「モリ」はあるし、巣作りに適した戸建ての家は多い。
来年以降も見られることを期待したい。
|
|
 |
| 2010年6月24日(木) |
| 「これぞリサイクル」に拍手 |
茨城県の茨木町にあるという「ゴミ収集所」の写真に拍手喝采した。
「もったいない」を世界に広めたいと、マータイさん以上に熱く思っているばあさんとしては、茨城町役場へ飛んでいって、係の町職員さんを握手責めにしたい気分。近頃まれに見る「上機嫌」にさせてくれた一枚の写真だった。
写真を見れば一目瞭然。何の説明も必要ない。背景を見ると、町中ではなさそうだが、それでも「車いす対応」と思われるかつての電話ボックスの形態からすると、障害者利用も義務づけられた後に設置されたボックスなのだろう。まだそう古いものとは思われない。その気になってみると、地面のコンクリートなどは新しそうに写っている。
それでも、携帯の普及速度には負けて、電話は取り外されてしまったのだろう。今では少し採算を割り込むとすぐに電話は撤去するらしいから。たとえこのボックスが利用できなくなると、生活に支障が出る障害者が居ようと、そんなことはお構いなしだから。「御身大事」で「企業の社会的責任」などは「死語」になっている今日では。
ボックスを撤去して更地にするのは、電話会社の負担ではなく、町の負担なのだろうか。とにかく、ボックスの撤去は、電話機の取り外しのように簡単にはいかない。取り外したら、粗大ゴミとしての廃棄もしなくてはならないだろう。「この場所には必要なくなっても、他の場所に設置が必要だから持って行く」などということは、考えられないご時世だから。
話が会社から出たのか、町当局から出たのかは分からないが、町としては、カラスの被害も風によるゴミの飛散も考えなくていい、絶好のゴミ置き場だし、電話会社としてもボックスを処分する手間と金が必要ないのだから、双方共に「願ったりかなったり」だったろう。話はトントン拍子に進み、あっという間に「ゴミ収集所」という看板に掛け替えられてしまったのだろう。
こんなリサイクルは、この町だけの専売特許にしておく必要はない。どんどん普及したらいい。ただし、このボックスのように障害者仕様になっていないと、ちょっと難しいかもしれない。立って電話をかけるだけのボックスは、このボックスの半分くらいしかないから、ゴミを入れておくのに狭いように思う。狭いと上に積むから、開けた途端にゴミ袋が転がり出てしまう可能性がある。そこがちょっと難点。
とは言え、何か工夫して、小さいボックスでもリサイクルできるようになれば、町の景観も変わるし、カラス対策も進むだろう。期待したい。 |
|
 |
| 2010年6月22日(火) |
| イスラエルはなぜ孤立しないのか |
|
イスラエルの「蛮行」は、時々報道されている。先日は支援船を拿捕して死者まで出したと大きく報じられた。
さすがに国際世論に懲りたようで、次の支援船は通すことにしたらしい。
大きな「事件」は、それなりに大きく報道されて、国際世論が動くが、小さなことは小さな報道しかされず、国際世論を喚起するまでには至っていないようだ。しかし、小さな日常的な「事件」の方が、現地の人々には堪えているのではないか。
今回の記事も写真付きでなく、たった1段の小さな記事になっている。
東エルサレムはパレスチナ人の居住区になっていて、将来はパレスチナ独立国家の首都と位置づけているにもかかわらず、イスラエルが東エルサレムで、パレスチナ人に住宅を充分供給しないため、無許可住宅をパレスチナ人が建てざるを得ない状況がある。にもかかわらず、無許可住宅だという名目で、パレスチナ人の住宅を破壊することをエルサレム市当局が承認したので、パレスチナ側の反発は必至。間接和平交渉にも悪影響を与える可能性がある。と報じている。
ガザの封鎖も同様だったが、自分たちが勝手に封鎖しておいて、封鎖を破ったからと攻撃する。今回も自分たちが勝手に許可を与えず、やむを得ず無許可住宅を建てたら、無許可住宅だから破壊しても構わないとばかりに破壊する。
どういう神経をしているのか理解に苦しむ。
残念ながらイスラエル人の知り合いも、パレスチナ人の友人もいないから、当事者の話を直接聞く機会はない。新聞などの報道から推察するだけになる。
ずっと以前、まだ今日ほどパレスチナ側の情報が届かなかった頃は、イスラエルが正義で、パレスチナはテロ集団だと思っていた。しかし、パレスチナ側の情報がかなりはいるようになると「今までの情報は偏っていたのではないか」と思うようになった。
まだ20代だったとき“栄光への脱出”という映画を見た記憶がある。あの映画では、イスラエル建国が“正義”の体現のような印象を与えた。あの映画も、長い間パレスチナはテロ集団のような印象を持つに至った原因のように思う。
あの映画は確かアメリカ製だったと記憶している。だからイスラエルの正当性を主張するような映画になったのだ。
生まれたときからイスラエルの攻撃に遭い、自分たちの虐げられた状況はイスラエルのせいだと教えられ、おとなと共に行動しているパレスチナの子どもたちは、どんなおとなになっていくのだろうか。「憎むな」という方が無理になっていくだろう。
そんなおとなを創りだしているイスラエルの正義とは何だろう。そして、そのイスラエルを支持しているアメリカとは何だろう。
どう考えても分からない。これがいつもの結論になってしまうのだが。これ以外の結論が出せない。
|
|
 |
| 2010年6月22日(火) |
| 権力は必ず腐敗する |
|
「権力は必ず腐敗する。たとえ聖職者といえども」という記事を見つけてしまった。
「バチカン 今度は汚職」「性的虐待に続き 威信低下は必至」「枢機卿、不動産取引に絡み」との見出しが並んでいた。
性的虐待で「司祭年」がとんでもないことになり、やっと教皇の謝罪で沈静化したのに、今度は汚職ときた。いったいどうなっているのだろうか。
枢機卿は教皇につぐ地位にある聖職者だから、相当な権力を持っているのだろうが、日本にいては、教会の「権力」ということの意味が、イマイチ分からないし、教会の社会的影響力についても見えてこないので、本当のところの深刻さは分からないのだが。
中世ヨーロッパを持ち出すまでもなく、カトリック国における教会の地位は、相当なものがあるのだろう。
以前コスタリカに行ったとき、進化の授業を見たことがある。冒頭教師が「この世界は神様がお作りになったのですが・・・」と言ったのには、目が点になったのを覚えている。日本でそんなことを言おうものなら「宗教教育は御法度」と言われかねないから。
その後の授業の進め方は、日本と同じ「進化論」だった。聖書の字句通り、神が7日間ですべてを作られたではなく、ビッグバンが起こり・・・と進んでいったのだった。
子どもたちもそれで納得するところが「さすがカトリック国」と感動したものだった。7、8割方がカトリックだとのことだが、その他の宗教信者子弟はどう感じているのか、保護者からのクレームはないのかについての質問をする機会がなかったから、詳細がどうなっているのかは、分からずじまいだったが。
カトリックの場合は、教条主義のプロテスタントとは違い、進化論も受け入れるし、そもそも進化論を称えたダーウィンもカトリック信者だったはず。
それはさておくとして、カトリック国の場合には、司祭や司教、枢機卿が行政の中に入っていくことがあるらしい。
今回の場合は、バチカン市国の「福音宣教省長官」を務めていた枢機卿が、ローマの不動産を不当に安く譲渡した疑いとのこと。
聖職者といえども人間だから、権力を握ればそれを行使したくなるものらしい。
または、人間だから親類縁者などがいる。彼らから頼まれれば、自分の地位や権力を利用して、便宜を図ってやりたくなるのだろう。ロボットではなく、宇宙人でもない人間だから、やむを得ないことなのかもしれない。
教会の権威が強くなると、聖職者も人間だから間違いを犯すことがあるという、当たり前の理屈が通らなくなるらしい。
「人間的弱さを神の助けで乗り切ろう」みたいなことを、信者には常に言っている聖職者自身が「オレは間違いを犯すはずがない」みたいな「うぬぼれ」を持っているのではないかと思ってしまう。
信者も「聖職者が間違いを犯すはずがない」と、過大な要求を突きつけないで、共に進む人間として扱った方が良いのではないか。そうすれば「威信低下」などとあわてなくてもすむだろう。
|
|
 |
| 2010年6月21日(月) |
| 補助犬養成が寄付頼みとは |
|
補助犬を育てる横浜の協会が、やっと指定法人の認定を受けたとの記事を見つけた。写真に写っている犬を、横浜の教会で見た覚えがある。「こんな小さな可愛い犬で、補助犬が務まるのかな」と感じた記憶がある。
後に写っている訓練士の方も、多分一緒にいた方だと思うのだが、記憶は鮮明でない。人間より犬を覚えているとは失礼かもしれないが、関心が犬にあったから、一緒にいた人間の方には注意が行かなかった。
その時に協会が「指定法人」を取るために、募金活動をしているとの話も聞いたような気がするし、いくらかのカンパを出したようにも思うが、あいまいな記憶しかない。聴導犬というので、犬の動きにばかり集中していたからだろう。
まだ訓練中との話だったが、すでに聴導犬として活動を始めているのだろうか。そこまでは記事がないので分からない。
それにしても、補助犬は必要性が高いはずなのに、盲導犬くらいしか「市民権」を得ていないところがあって、民間の協会が盲導犬育成の片手間に、細々と育成をしているだけの状況は、変化がないようだ。
法人の認定を受ければ、寄付を受けやすくなるとか、事業の拡大がしやすくなるなどの道が開けていくのだろうが、それにしても、手間も金もかかり、1年に数頭しか養成できない状況では、希望している障害者が待ちきれないではないか。
障害者の自立を図ることは、納税者を増やすことに繋がり、行政としても得策であるはずなのに、なぜ国が金を出して養成する機関を作らないのかが、理解できない。
今回の協会にしても、認可を受けないときは、盲導犬の利用者である障害者が、老後の蓄えを寄付して協会を設立したのだとのこと。
奇特な人がいなければ、事業を起こすこともできないなどとは、経済大国日本の名に恥ずべきことではないか。
金儲けばかりに熱心で、社会全体の幸福を考えない「エコノミックアニマル」などと言われてしまう我が国の状況を、何とかしたいと思うが、最賃レベルそこそこの年金暮らしでは、如何ともしがたい。
金持ちばかりを優遇する政治では、日本全体のレベルを上げることはできないし、そうであれば、いくら平均すれば所得が多くても、貧しい者は貧しいままに置かれてしまう。
感覚器に不自由があっても、補助犬を得ることにより、障害者ではなくなるのだから、国が本腰を入れて、養成すべきだと思うのだが。
大企業優遇税制の方が、日本を元気にすると信じて疑わない政治家連中では、話にならない。マスコミもそれに追随しているし。腹立たしいことこの上ない。
|
|
 |
| 2010年6月21日(月) |
| 司祭年閉幕ミサで、教皇が性的虐待を謝罪 |
|
「司祭年」とは何かが、教会に属していない者には分からないだろう。
「司祭年」とは、ローマ教皇が、よりよい教会を目ざして、司祭の役割を現代社会のなかで再度見直し考える「特別年」としたことによる。
「司祭年」が終了する6/11に、バチカンで「閉幕ミサ」が行われ、その説教のなかで教皇は「司祭職の聖性を祝うこの喜びの年に、司祭達の罪が明るみになり、特に児童に対する虐待で、神の私たちへの心遣いを世に示すはずの司祭職が、それとは全く逆の様相を呈してしまった」と指摘し、「こうした虐待行為が2度と起きないために、できることはすべて行うことを約束する」と語った。との記事にはあった。
また「私たちは、起こってしまったことすべてを、清めへの呼びかけとして受けとめましょう」とも呼びかけた。とも書かれている。
キリスト者独特で、他者から見れば「なにをご都合主義で言っているのか。反省が足りないではないか。だからまた再発するんだ。甘いぞ」と言われそうなフレーズになっている。
「きょうは水曜日だと思って油断せず、きょうが最後の日と思ってがんばれ」と言いながら「きょうは水曜日。まだ明日の木曜日がある」と考えて、絶望しないようにしろとも言われたとの話を、アウシュビッツから生還した司祭から教えられたと、尊敬している司祭から聞いたことがある。
どっちが本当なのかと思うこともあるが、どっちも本当だと思って、人生に対応することが良いのだと、今頃分かるようになってきた。
キリスト者の持つ明るさの根源が、ここにあるのだと思う。自分なりのせいいっぱいをした結果、うまく行かなかったり失敗したりすることがある。その時は次の機会に、またせいいっぱいをすればいいと考える。それにより、絶望にうちひしがれて、その場にとどまってしまったり、自ら命を絶ってしまうことなく、未来に希望を持って進んで行かれる。
単に「皆さん清めとして受けとめて、これからも元気でやりましょう」と言うだけでは、再発防止にはならないから、それなりの対策は考えてくれていることだという前提での「次の機会に頑張りましょう」ではある。
司祭の資質の問題はなかなか難しいらしいから、おいそれと無くなるかどうかは、疑問のあることは確かだ。虐待傾向のある者でも、司祭の絶対数が足りないと、切るわけにはいかないとの事情もあるらしい。
しかし、そんなことは言っていられないから、厳正な審査をして、虐待傾向のある者は切ってもらわねばならないし、虐待の事実があった場合には、隠蔽せずに対応してもらいたい。「仲間を裏切れない」みたいな気持ちを持つのだろうが、それが間違いの基なのだから、断固表に出さねばならない。
教会の持っている上意下達の体質を何とかすることも、根本問題ではあるだろう。上の言葉に逆らうのは、キリストに逆らうことだみたいな雰囲気があるようだが、そういう上下意識は捨てて、真のキリスト者として行動してもらいたい。
|
|
 |
| 2010年6月19日(土) |
| 男の顔も女並み |
10日も前の「旧聞」で、面白い記事を見つけた。面白いなどと言ったら「反フェミニスト」からは怒られそうだが。
1995年に、勤務先で大やけどを負い、顔や首にあとが残った男性が、労働基準局の労災認定が、女性に比較して低すぎるとして、男女平等を定めた憲法違反だと訴訟を起こしていた。
京都地裁が、等級の男女差は違憲との判決を出したことに対し、厚労省は控訴断念を決め、今年中に等級の見直しをめざすとのこと。
この判決受け入れにより、自賠責や被害者給付金の最低基準の見直しにも影響するとのこと。国土交通省や警察庁にも関わりが出てくるとは、面白い結果だ。
この裁判の原告側弁護士は「男女平等は当然だが、女性の等級を男性に合わせることで、給付額が下がることのないようにしてほしい」との談話を出したそうだが、これは重大な問題だ。
75歳からの「後期高齢者医療」の廃止を求めたら、65歳までに引き下げて、高齢者医療費を「応益負担」にしようとする動きがあるくらいだから、官僚の考えることは油断も隙もないこと。
「女性を男性並みに扱う」との名目で、低い等級に合わせることは充分あり得る。今後の推移を見守らねば。
それにしても「女は外見、男は中身」のような扱いで、男が外見を気にするなどは「女々しい」と思われていた社会の変化を実感できて愉快、愉快。
今時「中身」が良ければ外見はどうでも良いなどが通用するはずがない。
ラジオの時代ならばいざ知らず、テレビ時代の今日では「イケメン」であることが、タレントや俳優、歌手などの特別な職業だけでなく、どんな職業でも影響する時代なのだから、気にしない方が「遅れている」わけ。
「化粧品の売り上げなどから、女性の方が外見により高い関心を持っている」などという理屈が成り立つはずがない。
「反フェミニズム」論者の方々は、男性と同じにしろと言いながら、女性に有利な問題はそのままにするという論法で、男女は不平等で良いのだと言ってくる。
今回の判決に双手をあげて賛成することは、真の男女平等を願っていることの証明になると思うがどうだろうか。 |
|
 |
| 2010年6月18日(金) |
| なぜ小池さんの顔にシールなのか |
|
テレ朝の「スーパーモーニング」を見ていたときのこと。
消費税に対する各党の見解を所さんが解説した。各党の一覧が党首などの顔写真入りで、1枚のボードにまとめられていた。上段左端から自民、公明、社民などの既成政党が並び、下段にはみんなの党などの新党が並んでいた。
既成政党であるにもかかわらず、共産党は新党の最後、つまりボードの右下に置かれていた。
ボード作成者の意図はなに? 共産党は、このところにわかに、雨後の竹の子のごとく出て来た新党よりも小さい存在だということ?
本当はボードに載せたくなかったが、載せないとまた文句が来るから仕方なく載せたってわけ?
既成政党で、閣内離脱した社民党よりも大所帯の共産党が、一番最後とはどういうわけなのか。海のものとも山のものともつかぬ新党よりも軽い存在だということなのか。
どういう基準で政党を並べたのか、電話をかけて即答を求め、場合によっては、ボードを作り直して提示してもらいたいくらいだった。
そうは言っても電話をかけてごちゃごちゃ言っている間に、番組は次に移ってしまうだろうからと、我慢してみていた。
すると、もっとアタマに来る事が起きた。
それは、各党が消費税にたいして、どんなコメントを持っているかのシールを貼る場面だった。自民党は「まねするな」のシール、社民党は「反対」のシールなど、所さんのコメントを加えながら、次々貼っていった。
最後に共産党の番になった。共産党は志位さんの顔写真ではなく、なぜか小池さんの顔写真になっていたが。
「当然反対です」とコメントしながら、よく見もしないでというか、わざとボードをしっかり見ないでと言うべきか、とにかく「貼ればいいだろう」という調子で、小池さんの顔の上にシールをべたっと貼ったのだ。
他の党のシールは、顔写真とは反対側に貼られたから、シールを映しても顔ははっきり見えているのに、小池さんの顔だけが隠されてしまったのだ。
「そんなことまでして、テレ朝は共産党を出したくないのか」と思ってしまった。電話をしても「申し訳ありません。先を急いでいましたので、つい手元が狂って顔の上になってしまいました。以後気をつけます」くらいしか言わないに決まっているから、かけるだけ無駄と思ってかけなかった。
その場には、大谷さんという『赤旗』にも登場しているジャーナリストの端くれも同席していた。「それ顔が隠れていますよ。張り直してください」くらい言える位置にいたはずなのに、なにも言わなかったらしい。終わりまで張り直しはなかったから。
彼は性教育の問題の時「トンデモ発言」をした人物だから、やはり真の民主主義者ではないと考えて良さそうだ。既成政党でまっとうな主張をしている共産党をしんがりに置いても、その政党の重要人物である小池さんの顔にシールを貼られても、なにも言わないなんてエセに決まっている。
|
|
 |
| 2010年6月16日(水) |
| 十年一日というけれど・・・ |
|
「禁止行為多すぎて・・・」の見出しに「なにかな?」と目を留めた。「ローカルニュース世界編」となっているから、外国であることはすぐ分かったが。
北京の天安門広場近くにある歩行者天国「前門大街」の入り口に経つ、21項目もの禁止事項を示した標識に対する物議について報じている記事だった。
「十年一日のごとし」というけれど、北京はまだまだ標識が必要な状況なのだと、変な感慨を持った。
10年以上前になるが、研究会があって北京を訪れたときにも感じたし、その前初めて中国の西昌・成都などへ行ったときにも感じたことが、今も余り変わっていないことが分かったからだ。
初めて行ったときに、街には信号が余りなかったなかで、たまに信号のある交差点を通ることがあった。自分の進行方向は赤だったから、ごく当たり前に信号待ちをした。ところが、荷車を引いたおじさんなどが、ゆうゆうと赤信号を無視して渡っていくのだ。そのため、信号は信号の用をなさず、交差点の混乱は信号のない交差点と同様になっていた。 ガイドさんは「アラーっ」という我々の声に「信号ができたばかりで、なかなか意味が徹底されてないので・・・」と、自国の名誉に関わるからと弁解に努めていた。
あの頃は、確かに中国と言えば「発展途上国!」という感があり「そうだろうな。教育も徹底できてはいないだろうし。信号だって付いたばかりでは、意味が分からない人がいるだろうな。あのおじさんは田舎から出てきた人って感じだし・・・」と納得していた。まだまだ車もそれほど多くはなかったこともあり、今後改善していくのだろうと好意的に見ていた。
その後、5、6年経って訪れたときには、空港から市内までが大渋滞で、30分で行くはずが1時間以上かかるという始末だった。信号も増え、道路も整備されていた。それでも、信号無視でゆうゆうと渡る人は相変わらずだった。
今回の記事では、信号を守ろうレベルではなく「生活指導」的標識も多いようだ。「歩き煙草」「食べ歩き」「ゴミのポイ捨て」あたりは、日本でも標識を作る必要があるかと思われる内容だが、中国らしいものとして「痰吐き」「雑伎」「たこ揚げ」などもあるとか。しかしこれは、日本でも「軽犯罪法」違反になりそうな内容だ。実際にはたこ揚げを街の中心のホコテンでやる人はないだろうが。
雑伎は日本流では「大道芸」となるかと思うが、これは結構やっている人がいると思う。禁止になっているかどうかは分からない。
日本ではおそらく無いだろうと思うものに「銃や刀の持ち歩き」「焚き火」「物乞い」の禁止がある。銃や刀は「銃刀法違反」になるから、通常ではあり得ない。ホコテンでの焚き火はさすがにないだろう。物乞いに似た行為や、野宿は最近出ているのではないか。
日本の10倍以上の人口を抱え、教育も日本ほど徹底していない中国だから、色々標識にして「啓蒙」しなくてはならないのだろう。当局の苦労がわかる。
しかし、実際に歩いてみると、痰吐き有り、食べ歩き有りで、さほど効果がないようだ。と記事は結ばれているが、以前と比べてどうなのかも報じてほしい。以前と変わらないのなら、標識効果はなかったわけだし、それでも減少しているならば、効果があったことになるのだから。
十年一日というが、経済では日本を抜くという「経済大国」中国が、マナーでは「発展途上国」のままというのは、どうも納得できない。「衣食足りて礼節を知る」という諺もある。元々中国が本家の諺だと思っている。本家が諺通りになるのはいつの日なのか。
いずれにしても、標識や法律を必要としていることは、民意の低さのバロメーターになる。標識や法律が無くても、誰も行為をしないならば必要ないのだから。日本は標識を作らねばならぬ方向に進んでいるのか、作る必要ない方向に進んでいるのか。他山の石として考え直してみることも必要だ。
|
|

|
| 2010年6月10日(木) |
| 当事者抜きに物事を決めるとは |
|
「自立支援法『改正』案に抗議」「障害者抜きに決めないで」の見出しに「またかよ」と思いながら読んだ。
支援法裁判の和解条件に反する改正がされようとしているとのこと。
違憲訴訟の和解案で、自立支援法を廃止し、新法を制定することで基本合意し、当事者を加えた審議が始まっているなか、民主党が、自民・公明両党とともに、利用者1割負担の応益負担を残したままの同法「改正」案を国会に提出、成立させようとしている。との報道。
今回の「改正」案がもし成立すれば、新法の論議は腰砕けになり、成立がいつになるか分からなくなる可能性が高い。「改正したから良いじゃないか」という理屈が通るだろうから。
新法成立には時間がかかるから、それまでのつなぎとして現行法よりはましになっている「改正」法にすれば良いとの意見もあるかもしれない。一見親切そうで、その実いい加減な考えに基づく「お茶濁し」の論だが。
自立支援法にたいして、訴訟を起こしてまで「反対」を表明した根本が「応益負担」制度にあるのだから、どこをどういじっても、応益負担がそのままでは「改正」とは言えない。障害者の生存権に関わることだから、一歩も譲れない。
法律の制定に向けて、当事者の意見を聞かないなどと言うことがあり得るだろうかとの疑問もわく。
この間、やっとのことで成立した法律がいくつもある。肝炎救済、水俣病救済、被爆者救済、などなど。何十年来の運動の成果としての法制化だ。
その場合に、当事者抜きでの法制化があっただろうか。多少の差はあるものの、必ず当事者の意見を聞いての成立であったと思う。カネミ油症は、今救済法に向けての運動が進行中のようだが、やはり当事者の意見を反映するための手だてが取られている。
障害者問題になると、なぜ当事者の意見を聞こうとしないのだろうか。障害者差別があるからとしか考えようがない。
障害者は、自分で考える能力を持っていないから、こちらで考えてやらねばならないとでも思っているのだろうか。
交渉の場でも前面に出てくる可能性の高い「脳性麻痺」の方々は、言語障害がひどかったり、不随意運動があったりして、見た目では「能力が低い」と取られてしまう場合がある。全介助の方も居て、本人は何もできない「無能」者だと思いこまれてしまう場合もある。残念ながら「障害者」としての印象を強く持たれる存在のため、すべての障害者を代表するような形で、障害者差別を生みやすくしているかもしれない。
障害のあることと「能力」の有無は関係ないことだとの理解が進めば、当事者を入れない審議などできなくなるのではないか。
法案成立に関わりの深い官僚の皆さんに、障害者運動に加わってもらって、障害者と日常的に接する機会を持ってもらいたい。そうすれば、少しは理解が広がるだろう。
「自分たちとは関係ない存在」としか見ていないから「やってやる」という態度になるのではないか。
|
|
| 2010年6月9日(水) |
| 首から下は20代?! |
 |
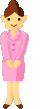 |
|
先日近くで行事があり、手伝いに出かけた。グループのメンバーも一緒で、あれこれ仕事をしているところへ、人混みから浮き出したように見えるご婦人がやってきた。白いミニスカートで、白っぽいジャケットを羽織り、白っぽいつば広の帽子を被っておられた。
細身の体型に、コーディネートもばっちりで、素人離れしていた。
「あれは○○さんのお連れ合いよ」と言われて「首から下は20代」と言ってしまったが、あわてて口をふさいだ。しかし、改めてまじまじと見てしまった。
○○さんは古希を越えておられる。その連れあいとなると、やはり古希を越えておられるのではないかと、お顔付きから判断した。
「モデルをおやりになっていたのですか」「アナウンサーご出身とか」「タレントだったなんてことは」と、矢継ぎ早の質問攻めに「いやそんなことはないよ」「何もしていないよ」との返事。
あのファッション感覚は、どこで磨かれたのだろう。ご本人に聞く機会がなかったから、野次馬根性がムラムラと湧いてきた。
以前ご自宅の前を通りかかったときに、車を待っているお二人に出会ったことがある。そのときは「年配のご夫婦」という印象で、特に何のインパクトも受けなかった。
あの時は、普段着だったからか。皆さんの前に出るからとよそ行きにすると、首から下は20代のようになるらしい。
「おとな可愛い」とかが今のトレンドらしいし、好きな服を着ることは本人の自由だから、他人があれこれ言うことではない。「人権」だの「自由」だのと言っているツッパリばあさんとしては「素晴らしい。大いに結構。大賛成」と言うべきだろう。
だが、双手をあげて賛成できない、喉に骨が刺さった気分になるのはなぜか。
「おとな可愛い」のターゲットは30代の女性のようだ。先日のテレビでは、40代、50代の女性が「私たちだって」と言っていたから、そのうち50代も20代と同じになるのかもしれない。そうではあっても、70代が20代になるには、まだまだ時間がかかるのではないか。
なんといっても、悔しいことには、肌のしわや皮膚のたるみはどうしようもない。くだんのご婦人も、膝とそれからでているモモの皮膚はたるみがでていた。首にはよこしまがある。頬は地球の引力に逆らえずにいる。というわけで、服と中身がちぐはぐの感が否めない。着こなしてはいるのだが、服が勝ってしまっていて、人間が「着させられている」感じに見えてしまう。
年相応の地味な服を着ろなどとは口が裂けても言わない。先日のテレビで「若さを保つ」ポイントのひとつに、ピンクやオレンジなどの「明るい色を着る」ことが上げられていたので、我が意を得たりと思ったばかりだし、周りには「赤や黄色なんぞ着て」と言われているのだろうから。
明るい色で、若々しいデザインで、しかし、20代や30代の「若造」には真似のできない、シニアならではのファッションは生まれないものか。
その時が来たら、新しい服を買うことにしよう。それまでは、今ある40代、50代に買った服で間に合わせておこう。
|
|
|
 |
| 2010年6月9日(水) |
| まだ解決していない無国籍児問題 |
|
離婚後300日規定のために、戸籍ができない子どもたちが、年間3千人ほど生まれているとの記事が目に留まった。
以前にも無戸籍児のことで書いた記憶がある。あの時は、近々改正されるのではないかと思っていた。あまりに現在の科学的知見とかけ離れた法律だから、改正されて当然と思ったからだが。
明治時代に制定された法律が、現在でも生きているというのが驚きだが、法律などというのは、いったん制定されてしまうと、時限立法とか何年後に見直しとの規定を入れてない限り、ずっと続いてしまうものらしい。
明治に制定された法律は、戦後の新憲法制定との関わりで、すべて見直され、すべて改正されていると考えてしまうが、60年ほど前の社会状況で、大きな矛盾が出ないものは、そのままにされてしまったのだろう。
その法律によって不利益や不当な差別を受ける人が異議を申し立て、異議の申し立てが増えてきたら、見直しを検討し、論議の結果異議申し立てが政党と認められれば、改正されるという筋道を取るのだろう。
障害者関係の法律改正に関しては、いくらか事情を知っているので、それから類推するのだが。
明治時代にはDNAによる親子鑑定などというものはなかったから、妊娠期間の300日から推定するしかなかったのだろう。
しかし現在では、DNA鑑定によれば、ほぼ100%の確率で、生物学的な親子関係ははっきりできる。
それにもかかわらず、依然として法律が改正されないのは、改正によって不倫を助長するとの誤解があることによるらしい。
今時、300日条項の有無が不倫を助長する、などという考えを持つ人間がいるのかと思うのだが、法相はその立場を取っているらしい。条項があるから不倫を思いとどまったり、出産を止めるなどという考えを、真面目に論議している人達は、よほどの世間知らずか、別の理由で改正したくないのを、カモフラージュするために条項を利用しているとしか考えられない。
不倫をするかしないかは、条項の有無とは何の関係もないと思う。これは「飛んでる」私の考えだけでなく、きわめて「常識的」と思われる、近所の同世代の方も言っていること。彼女でさえあきれるような、今の常識からは外れていることのために、何の関係もない子どもたちが、戸籍を取得できずに、さまざまな不利益を被っているのは許せない。
子どもは社会の宝とか、社会で子育てをと言いながら、矛盾した行動を取っている。
おとなの責任として何とかしたいものだ。
|
|
 |
| 2010年6月4日(金) |
| 韓国での同性愛事情 |
|
「同性愛扱い反響」「アジア通信 韓国」の見出しに「おやっ?!」と思って読んでみた。
韓国のテレビドラマで、同性愛を扱い、視聴率がドラマ最高の20%になったとの記事だった。
韓国では10年前に、芸能人が同性愛をカミングアウトして話題になったが、いまだに否定的な考えが多く、ドラマのテーマになることはなかったとのこと。
日本でも、最近まで同性愛は公表されにくい問題だった。今は、仮屋崎さんのような「芸能人」ではない方でも、カミングアウトされるようになったが、10年前には「同性愛がわかる本」などの「啓蒙書」をせっせと出さねばならぬほどに、差別と偏見は強かった。
今はそれが無くなったかと言えば、決して無くなってはいない。特別の才能を持った人ならば許容されるようになってきただけで、本質的な解決にはほど遠い現状。
同性愛に対する世代の違いは著しいと思う。若者たちには、許容する人が増えているだろうが、熟年世代以上はかなり難しいだろう。「人権」ということに敏感な「革新的」「リベラル」などと言われている人でも、同性愛の問題は「別」らしい。むしろ「人間性」を疑うような言動すらする。
まだまだと思っている日本だが、韓国に比べればましではあるようだ。
ドラマのなかでは「申し訳ない。死ねと言われれば死んでもいいが、こんな人間が僕です」というセリフがあるとのこと。
日本でも、特に思春期の男の子のなかには、自分が同性愛であることに失望して、自殺をしたという例があると聞いている。しかし、それは最近のことではない。同性愛の自助グループなどができ、自殺する前にコンタクトを取って、自己肯定感をもてるから、自殺には至らなくなってきたようだ。
イスラム圏では、いまだに同性愛者は抹殺されてしまう国もあるようだから、同性愛と死という問題は、フィクションではない状況はある。
それでも、日本で今ドラマが作られたら、韓国のようなセリフにはならないと思う。前後が分からないから、どういう設定でのセリフかははっきりせず、ピントはずれになるかもしれないが、家族に告白する場面でも「死ねと言われれば死んでもいい」とのセリフは書かれないと思う。
性的指向の問題は、嗜好の問題ではなく、本人の選択によるのではないことが、周知徹底されれば、解決に向かうのではないかと考えるのは甘いか。
「性の左利きのような存在」であることを理解すれば、無用の差別や偏見を持つ人は確実に減少すると確信しているのだが。特に「メガネ」をかけさせられていない若者に期待したい。
|
|
 |
| 2010年6月2日(水) |
| 本当に専業主婦思考に回帰したのか |
|
「『専業主婦派』の妻増加」の報道があった。'08年調査結果の分析から分かったとのこと。
「20代、価値観回帰?」としている。テレビのニュースでも、若い女性が伝統的価値観を否定するこれまでの傾向に、変化の兆しが見られると分析していた。
他方、結婚や少子化問題に詳しい専門家からは「非正規労働が増え、正社員でも長時間労働で疲弊する状況があり、女性の間で仕事への意欲が低下している。主婦になって子育てに専念した方が楽と考えるのは当然」と指摘する声が出ている。と書かれている。
数字のマジックで、数字だけ見て「伝統回帰」などと決めつけるのは早計だと思う。
専門家が指摘するように「仕事も家庭も」が両立しにくい現在の働き方のなかでは、主婦になって楽をしたいと考える女性が増加するのは当然だろう。特に、これから結婚を考える20代の女性としては、両立が難しい道を選ぶよりは、楽な道を選びたがるのが自然の成り行きだ。
今の20代は、我々シニアと違って、育ちの中で、歯を食いしばって頑張るなどという体験をしないできてしまっただろうから、少しの我慢もしないで済むならば、しない道を選ぶという傾向が強いだろう。
専業主婦が、共働きよりも価値が高いとか、専業主婦の方が優雅な生活だと考えているのではなく、自分がより楽に生活できる道を考えたとき、専業主婦の方がいいやということになっているのではないか。伝統文化に対する価値観が上がったわけではないと思う。
統計では、専業主婦の賛成割合が55、3%で最も高かったとの結果だが、これも至極当たり前の話。自分の立場を肯定しなければ生きて行かれないから、専業主婦になった自分を「これで良かった」と納得させるためには「専業主婦がいい」と答えざるを得ないだろう。
本当に専業主婦を肯定しているのでもなく、これを望んでいるのでもないことは、実際に結婚した女性では、共働きをしている割合が結構高いとの統計もある。「専業主婦になりたかったが、家庭の経済状況で、とても専業主婦ではいられない」と働く場合。「専業主婦では、自分の能力が充分生かせなくて、やっていられない」などの理由で、共働きをする女性も多いとのこと。
明治以来の女性のように、女だから学歴はいらないとか、女は黙っていろとか言われて育ってはいない今の若い女性が、よほどの子ども好きとか、家事好きでない限り、主婦という立場だけで、満足して暮らしては行かれないと思う。
それの証拠となると思われるのは、50代、60代では専業主婦の賛成割合が、依然として低下傾向にあるとの結果だ。「専業主婦でやってきたが、これで良かった」と思っていない女性が多いことを物語っている。今20代の女性で、専業主婦がいいと言っていても、将来的には否定する可能性が高いと思う。
「仕事も家庭も」ができる社会を作った段階で、専業主婦がいいという女性が、どれくらいの割合になるのかを見なければ、専業主婦に賛成する女性が増加しているかどうかは分からないと思う。
|
|