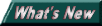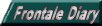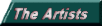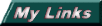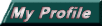|
 |
 |
|
|
  |
I cheer the post entertainers.
このページは、21世紀に活躍する芸人さんを応援してます。 |
|
|
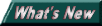 |
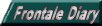 |
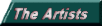 |
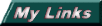 |
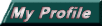 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
 公演を見た感想を中心に書いてます 公演を見た感想を中心に書いてます  |
|
|
| 僕の独り言 |
|
|
| 2002.06.23 愛山・喬太郎二人会 |
|
|
新作に独特の光を放つ両名の初二人会へ行ってきました。
○神田春陽 講談 吉岡憲法(漢字不明)
久しぶりに春陽君を聴いた。武芸者は体に入ってきたようだ。クスグリも上手くなってきて、お客さんの笑い声もチラホラ。
○神田阿久鯉 講談 柳沢昇進録〜お歌合わせ
いつもの講談会と比べると、若い女性客が物凄く多いのでビックリした。大変心強い。とマクラで話す。確かに、講談は女流が多い為かオッカケの若い女性は少ないようだ。講談界にも若きプリンスは欲しいな。
○神田愛山 講談 高野長英
愛山先生は、実は少年時代にさん喬師匠の熱烈なファンだった。と、さん喬師と愛山先生の出会い等や喬太郎師との二人会開催秘話をマクラで紹介。
喬太郎師と二人会をやろうと思ったのは、彼の新作「捨て犬」というタイトルを聞いた時だそうです。古典もきっちりと演じ、個性的な新作を演じるという彼に、自分と同じ臭いを感じたそうです。確かにそれは言えます。
○柳家喬太郎 落語 小言幸兵衛
30分たっぷりと聴き応えのある小言幸兵衛だった。前半と後半で幸兵衛の性格が変わっていく。
仲入り
○柳家喬太郎 落語 寿司屋水滸伝
ウルトラマンコスモスのムサシ隊員の傷害事件に対する気持ちをマクラで話す。初代からガイヤまで、地球を守ってきた彼らに顔向けできるのかと、声を大にして怒りをぶちまけていた。
根多の方は新作。ある寿司屋の最後の板前が辞め、洋食の修行しかした事の無い主人が店を続ける事にそこに助っ人職人登場?・・・・・
ハチャハチャになっていくストーリが妙の、ご存じ寿司屋水滸伝でした。
○神田愛山 講談 真剣師
私小説講談「品川陽吉シリーズ」からこの作品。
昼間やくざに殴られた品川陽吉は、その夜中野の行きつけのバーに顔を出した。そこで真剣師(かけ将棋差し)の島田と名乗る男とであうが・・・
ドン底にいる人間を描いた愛山ワールドな作品です。(勝手に品川陽吉シリーズを呼んでます。)初めてこの先生の新作を聞いた喬太郎ファンはどういう感想を持っただろうか、気になるところです。
次回は7月20日(土)
|
|
|
| 2002.06.16 鈴本早朝寄席 |
|
|
久しぶりに、日曜午前中の名物?の鈴本早朝寄席に行ってきました。落語協会二ツ目さんの勉強の場と言う事でもあり、1時間半500円で楽しめる寄席です。
何時もは4名ですが、今回は3名の出演ということで、一人30分。各々長講一席となりました。
さて、そのの様子は・・・・
○柳家太助 落語 幇間腹(たいこばら)
話題と言えばサッカーワールドカップ。太助さんも楽屋内でチケット取れない・取れた根多を中心にマクラをやる。
根多のほうは、寄席では省略されることの多い、一八が若旦那のいる部屋に入るまでの所もたっぷりと聴けた。
○柳家さん光 落語 蛙茶番
マクラ噺はやっぱりワールドカップ。
根多はお馴染みの根多。小間物屋のミーちゃんにホの字の半次が上手く演出されていて良かった。
○三遊亭歌彦 落語 手水廻し(ちょうずまわし)
手水廻しとは、大阪だけの言い回しで、顔を洗う事。とマクラで解説を聴いてからこの根多に入る。この解説がないと面白さが全然伝わらない根多。 初めて聴いた根多だったが面白かった。
それぞれたっぷりと聴かせて貰えて、得した気分。
早起きは三文の徳は嘘じゃ無かった。
それにしても、柳家は古典が上手い。
|
|
|
| 2002.06.08 本牧亭講談定席 |
|
|
お江戸両亭で暫定開催している、本牧亭講談定席の6月興行の様子を少し書こう。
○京子 三方ヶ原合戦
五郎政宗を勉強するにあたり、本物の刀を知る必要があるので、美術館へ行って刀を見てきた。と、その時の感想をマクラではなす。
根多は五郎政宗ではなく、三方ヶ原だった。顔を紅潮させての修羅場読みでした。
少し前にTV番組で、この三方ヶ原での勝敗を決めた両軍のタクティクスの違いが分かりやす説明されていた。この講談は分かりにくい。
○阿久鯉 まきのひょうご 前編
先日の国立演芸場での「女流の夕べ」の感想等をまくらで話す。
根多は、まきのひょうご(漢字不明)。初めて聞いた読み物だった。
○陽司 河村瑞軒
今旬の話題であるサッカーについて陽司さん流講釈のマクラ。
講談ファンのおじいさん達にも分かる解説の一コマとして、オフサイドは、抜け駆け禁止令!ん〜〜分かりやすい。
本題は古典。17世紀初頭のベンチャー男である河村瑞賢の物語。関西弁と江戸弁とのスイッチ切り替えの妙が面白い。大阪出身の陽司さんならではの技だ。
○愛山 出世の高松
前座時代、ろ山先生に稽古をつけてもらった根多とのこと。初めて聞く読み物だった。
○昌味 義士銘々伝〜大石瀬左衛門
剣の腕の強いとある道場の娘。この娘に勝ったら、その侍のもとへ嫁に嫁がせるという本人不在のとんでもない試合をしている元禄時代が舞台の物語。
○松鯉 連続 幡随院長兵衛
長兵衛の贔屓にする力士が、その長兵衛のライバルが贔屓にしている力士と対戦することに…
来月からの本牧亭定席は、新居で装いも新たに始まるそうです。今月の定席案内に書いてありました。その名も、「黒門町本牧亭」乞ご期待。
|
|
|
| 2002.06.04 日本講談協会女流の夕べ |
|
|
神田一門会@日本講談協会の女流の夕べへ行ってきました。今夜はワールドカップ日本代表初戦という歴史的な日でもありました。
メモを紛失したのでゲストさんの名前が不明なのはゴメンナサイ。
○カムバック源左衛門 京子、きらり、紅葉
トップは前座さん達による合同修羅場読み。立体講談的な立ちでの動作も入っている。この合同修羅場読みは、神田派のお家芸のようです。
様々なイベントで、この形の芸を披露しているのを拝見している。
根多は鉢木から源左衛門の鎌倉駆けつけの場面。前座さん時代の必須科目の修羅場読み。
ご当人達は得意科目かな?
○ジャンヌダルク 立体講談 山吹
黒のスーツに白の蝶タイ姿の山吹さんが現れた。洋服姿の高座は初めて見る。いつもの着物姿とはイメージが変わる。 まるで手品師?(笑)
慌ただしく感じる程の速さで進んでいる。時間が押しているのだろうか。立ちでの仕種は役者のようには上手くなかったが、語りは良かった。根多下ろししたばかりのようだが、レパートリーに加わると持ちネタにバリエーションがでて良いと思う。
○人魚姫 立体講談 紫、昌味、阿久鯉
地の語り(ナレーションン?)に紫先生。人魚を弓で射った侍とその娘役に昌味先生。その他の人々を阿久鯉さんで担当。
気の違った娘役の昌味先生が良かった。この先生は元気の良い男子が講談では上手いと思っていたが、女性役も上手くなった。女性を主人公にした新作の自作自演を最近やっているからかもしれない、
○仲入り後 口上
真打、二つ目の7名が舞台に並ぶ。左下手から先輩順に、陽子、紫、紅、茜、昌味、山吹、阿久鯉。(敬称略)
茜さんが「ここまでは30代」と紅さんと自分の間に手で線を描く。紅さんはムッとした顔。お客さん爆笑。 各自自己紹介をする
最後は「合戦修羅場」と題する修羅場バトル。
幸村大阪入城チーム vs 義士伝〜寺坂の口上チームに別れての読み比べ。普段の講談会ではなかなか修羅場は聞かれないので、面白い趣向でした。
○美人への花道 紙芝居 茜 昌味
体重が不自由な女の子「えり」が主人公のダイエットもの。確か昌美さんのオリジナルだと思ってがどうなのだろう。絵も定評の茜さん。ほのぼのとするが、笑いのツボはかかさない絵と語りで茜ワールドに包み込まれました。
途中、昌味さんが登場し、ダイエット用品読み立て修羅場もあり、楽しい、女性らしい根多になっていました。
○マリリンモンローは紅だった 立体講談 紅 阿久鯉
何故かこの根多のマクラに阿久鯉さんによる、金棒お鉄。このまくら噺の意味不明。
金棒お鉄の抜き読みが終わると、椅子が一つ舞台に持ち込まれる。舞台上手から金髪のカツラを被った紅さんが登場。着物から一瞬(に極めて近い時間と言っておこう)にピンクのドレスに変わる。モンローがそこにいた。
普通のOLだった時代から亡くなるまでを、モンローの一人語りの形式で物語は進む。
これが紅先生のあのモンローか。
○番長皿屋敷 講談ダンス 陽子 ゲスト
舞台の左角に高座があり、陽子先生が座る。中央の空間はゲストさんのダンススペースになっている。客席の照明も暗くなり、ほとんど芝居の演出だ。
陽子先生の語りと同期をとり、ダンスがはじまる。ジェスチャーゲームの様に読むまんまを踊るのではなく、登場人物の心情を動きで表現しているようだ。
講談とダンスのコラボレーションは初めての体験だった。
物語と別の物は伝わってくるようだが、よく分からない。
日本講談協会の多数勢力となっている女流達が勢ぞろいの会。普段の講談会では無い変わった演出・趣向あり。華が有り、良い会だった。また次回を計画してほしいものです。
|
|
|
| 2002.05.19 板妻映画祭〜サイレントA |
|
|
熱き心を書き記したMS−word原稿が冷たい異常終了のお言葉で消されてしまい、書く気力が萎えてしまったので、エッセンスだけ紹介します。
板妻生誕100年を祝う日本映画大手5社協賛のこの企画。僕が行ったのはサイレント映画に活弁が付く企画でした。
○佐々木亜希子 活弁 小雀峠
舞台上手からベージュに大柄な意匠のワンピースを着た若い女性がスポットライトに追われながら登場した。弁士と自己紹介し、映画の解説をする。今の時代に活動写真弁士と言うプロの職業が存在する事に驚いたが、若い女性が弁士とは更にびっくり。
ソフトタッチな活弁でした。こういうのもあるんだ。
作品について、大正12年公開。板妻21歳。ヒールのわき役
↑
だれが板妻かよくわからなかった。
○神田北陽 活弁 逆流
黒紋付袴姿で、舞台上手から小走りで登場。やや上がり気味か。
「今日も超満員です。立ち見ですごい状態です。お客さん、後ろは見ないで下さい!!。」
「字幕はお客さんが読んで下さい。私は別の事を喋ります。」ツカミはOK
「上の人、私がお願いしますと言ったら回してください。」
弁士の席に着いてからもパニクる北陽さん。
映画は良かったんじゃないでしょうか。
でも主役は北陽さんだったような・・・
○片岡一郎 活弁 坂本竜馬
青色の着物姿で登場。
「講談師よりもマイナーな職業の弁士」
「弁士は神田北陽 その他 と紹介された」と反撃。これもツカミはOK。
板妻事務所制作のこの作品を上映。板妻氏は一度坂本竜馬をやりたかったそうな。
昭和3年という時代劇大当たりの年の作品という。
最後の死に方が印象に残る。
弁士は控えめな語りが良いのかもしれない。
|
|
|
| 2002.05.04 最後の立川談志五夜 [不完全落語大全集] |
|
|
横浜賑わい座に、談志師匠の独演会を聞きに来た。連続5夜の独演会だ。師匠はこの寄席の近くに独演会のためにリゾートホテルへ滞在して、高座に挑んでいるとの事。この企画を逃すと師匠の落語を聴く機会を逸すると思い、先週賑わい座の2階でキップを購入したのだった。
二階席のキップだが、見栄え音の通りはどうだろう。と多少不安混じりで席についた。
○立川談志 落語 堪忍袋
幕が上がると、前座さんでは無くいきなり談志師匠のめくりが見えた。舞台上手からバンダナを絞め、着物に袴姿の師匠がゆっくりと出てきて高座に上がった。
まくらでは昨日の反省、自分の落語について、過去の優れた芸人や感動した映画等をたっぷり30分程語る。肉声でも二階席まで鮮明に聞こえる。丁度僕の前の席が空席だった関係もあり、高座姿もはっきりと見え、動きは一階席よりかえて良くわかる。
堪忍袋に幾人もの人々がストレスの元凶を怒鳴りちらしていく所は熱演だった。現役健在をアピールした。
お仲入り
○立川談志 落語 田能久(たのきゅう)
前高座の出来がよかったからか、機嫌良く後高座のマクラが進む。
この根多は初めて聴く根多だ。
通称田能久と称する旅役者がある村から移動するため、山を二つ越えることになるが、この山中で、大蛇と遭遇する・・・・
民話が原作か民話かもしれない。大蛇の性格を表す台詞まわしは、談志師匠の地そのもので、面白かった。
高座が終わり幕が締まるが、拍手が続く。再度幕が開く。談志師匠が高座に居た。田能久の解説や、工夫した点などをアンコールのお礼に話した。そして本当に幕がしまる。
昨日の出来が師匠には不満足らしいが、今回は上出来だったようで、最後まで機嫌が良かった師匠だった。 ぼくも満足だった。
|
|
|
| 2002.05.03 快楽亭ブラック毒宴会 |
|
|
過激な内容で一部熱狂的なファンを喜ばせている快楽亭ブラック師匠の独演会へ行って来ました。
○快楽亭ブラ男談次 落語 まんじゅう怖い
二番弟子が前座を勤めます。
○快楽亭ブラック 落語 反対車
クレヨンしんちゃんの予定でしたが、今度の映画が面白くなかったので予定を変更して、この根多をやったそうです。
○快楽亭ブラック 落語 髪結新三 後半
この根多にはブラック師の毒を入れる必要はないようだ。古典のまんま演じる。
反対車を終えても下がらずに、汗を手拭いで拭ってそのままこの根多に突入した。
本会への気合いが感じられた。
○元気いいぞう 超過激なお歌
みんな元気?
「いいぞ」、「いいぞ」
の元気いいぞう先生の登場です。
内容はここではかけません。
曲のタイトルで書けそうなもののみご紹介。
「もしも月経が上がたら」、「北朝鮮が攻めてくる」、「死体としたい」
○快楽亭ブラック 落語 SM太鼓腹
内容は書けません。さげを終わった後お辞儀をしている場面の格好を紹介します。
上半身裸で、縞のトランクス一枚の姿。赤いロープで亀甲縛りをしたブラック師がお辞儀をしていますです。はい。
|
|
|
| 2002.05.01 神田山吹の会 |
|
|
西川口のTHE MOMOという店で開かれた神田山吹一人会。
ここ最近は地元埼玉での活動が目立ちます。
○神田山吹 講談 伊達家の鬼夫婦
赤い花柄の着物で登場です。顔は歯痛の腫れはすっかりひいて、元どうり健康になったかといえば、今度は目を患ったようです。メガネをかけていました。
根多は「獅子のホラ入り、ホラ返し」でお馴染みの読み物。講談が初めてのお客さんが多かったそうで、その人達にもわかり易い根多だったと思う。
槍を衝いたり、竹刀を振り回したり(扇子だけど)の熱演でした。
|
|
|
| 2002.04.30 鈴本4月下席 夜の部 |
|
|
この下席夜の部は、昨年秋、真打昇進した新作落語の三遊亭白鳥師がトリを勤めます。
鈴本の番組表には白鳥師のチャッチコピーは、「奇想天外新作落語のホープ」となっていました。
様子をセレクトで書きます。
○柳家ごん白 落語 牛ほめ
おなじみの根多。
○五明楼玉の輔 落語 紙入れ
「人の女房と 枯れ木の枝は 上り詰めたら命懸け」
という川柳がありますが、間男と鈍感な亭主の噺。この根多は好きです。
○柳家三太楼 落語 動物園のライオン
ナンセンスなストーリが面白い。すっかり定着した新作の秀作を三太楼師が好演した。
○三遊亭白鳥 落語 マキシムド飲んべえ
白鳥の湖の出囃子にのって白鳥師の登場。
先日の落語ジャンクションで披露したこの根多をやった。多彩なボケとツッコミのクスグリが面白い。
|
|
|
| 2002.04.27 一龍斎貞水と講談を聞く |
|
|
横浜にぎわい座のこけら落とし興行の一貫で行なわれた講談デーの夜の部へ行って参りました。
出来立てピカピカのにぎわい座に到着。2階が展示やお知らせ、チケット販売コーナ。3階4階が客席入り口となっていた。客席は1階席(ビルの3F)と2階席(ビルの4F)合わせると300名は収容できると思います。
○前説
小南陵先生、貞水先生に、陽子先生がMCとしてインタビューする形で進められた。
「講談とは」と言う質問に小南陵先生は「地の面白さ」貞水先生は「俺がしゃべると講談になる」とお二人の個性がよく現れている回答だったと思う。
○神田北陽 講談 谷風の情け相撲
前座さん無しで、トップは北陽さん。大師匠に囲まれて緊張しているのか、いつもの弾ける感じが無い。
根多はお馴染みのこの読み物。北陽さんは5月にも出演予定。
○旭堂小南陵 講談 難波戦記〜荒大名の茶の湯
関東と関西の講談の違いは...ということで革で巻いた張扇と小拍子(拍子木の小型版)の説明がった。上方では張扇は紙じゃなくて革をまくのか。網片方には扇子じゃなくて小拍子を使うのか。これは上方の噺家さんもつかいますね。
根多は一言で言うと講談版「本膳」と言えば落語ファンには分かりやすいかも。フィーリングカップル5対5で言えばの五番目の役が福島正則。
俳優としての小南陵先生は見たことがありましたが、講釈は初めて聞きました。今回の読み物はコメディでしたが、真面目そうな印象をうけました。
○神田陽子 講談 与謝野晶子一代記
前節でのMCでは淡い桜色の着物。そして高座では藤色の着物に着替えて登場です。昼の部も有ったので、一体何着の衣装を持ってきたのか。
根多はエンターティナ講談。楽しく聞けた。芸協の定席では1高座15分程度なので、今日はタップリと陽子講談を堪能した。
○一龍斎貞水 講談 兜奇談
貞水先生は昨年の夏のおばけ以来久々に拝見しました。根多は講談版「火焔太鼓」といった内容の読み物だった。
講談協会の会長に就任されたとのことで、益々パ貞水節ワーアップか。
|
|
|
| 2002.04.24 落語ジャンクション |
|
|
久々に落語ジャンクションへやってきました。今回は白鳥師と師岡氏の二人階という企画。満員の中野小劇場でした。
定刻開幕。
先ずはお二人による前説から始まる。
師岡氏は、最近俳優としての活躍が目立つ。NHKの大河ドラマでは、信長の時は隠れキリシタン。北条時宗では、山賊。今年は何と足利義昭役にまで出世。
片や白鳥師は現在鈴本夜席で主任をしている。今夜の代演は何と円丈師・・・と近況を語り、今日のメニュー紹介へと噺は盛り上がった。
○快楽亭ぶら汁 落語 新聞の勧誘(仮称)
この春、社会人一年生になった主人公のアパートへ新聞の勧誘員が訪ねてきて・・・
○三遊亭天どん 落語 せっかくだから(仮称)
マンションの401号室に引っ越してきた新婚さん。その家へ引っ越し祝のお返しに近所のおばさんがやってきて・・・・
いつものだらだら噺絶好調。
○三遊亭白鳥 落語 まきしむ・ど・のんべい
板橋で居酒屋を営むおばあちゃんとその孫のチエ。チエはOLで今日はおばあちゃんと、チエの行きつけの銀座マキシムへフランス料理を食べに行った。おばあちゃんは、自分の店でもフランス料理っぽくやってみようと思うが・・・・
○モロ師岡 一人コント
元気で病院通いをする老人達の物語を熱演。
お仲入り
○モロ師岡 一人コント
落語家の主人公が18年前の中学生の時埋めたタイムカプセルを掘り返しに、郷里へ帰ってきた。そこで見たものは・・・・・
チューリップハットに派手な柄のズボン。あのズボンは売り物だったのだろうか・・
○三遊亭白鳥 落語 神社の裏で(仮称)
銀行強盗で3000千万円を盗んだ男二人。その金を埋めた神社へやってきた。掘り返そうとしていると、ブラジル人の男の子が現れた・・・・
白鳥さんの根多にしては珍しいシチュエーションの根多。最後は少しホロっとさせる。人情噺っぽい内容になっていた。
|
|
|
| 2002.04.20 神田紅独演会 |
|
|
会場1時間前の5時に国立演芸場到着。整理券を貰う。この時点で100番台。前売りだけで完売状態となった神田紅さん25周年、一門旗揚げ披露講演会へ行きました。
○神田紅葉 講談 黒田節の由来
師匠へのお祝いということで、紅先生がおめでたい席で口演するこの根多を読む。
国立の超満員のお客様の前で、大分上がっていたようだ。
○春風亭鯉奴 落語 粗忽の釘
慌て方が地味。もっと派手に演じた方がいいかも。
○神田陽司 講談 青龍刀権次
山陽師匠の十八番のこの根多を口演。最近この根多を口演することが多い。
着物は本牧亭でトリをとった時に着た着物だった。最近のお気に入りか。
○神田紅 立体講談 滝の白糸
紫の着物で登場。
泉鏡花作のこの物語を熱演。僕は二度目の体験となる。
講談や落語の口演時のライティングと、芝居のライティングはまったく異なる。今回の芝居講談の場合はライティングが中途半端な印象を受けた。もっと芝居のように演者の感情表現を引き立たせる照明だともっと良かった。
殺人シーンの照明効果はインパクトが有って良かった。
会場では泣いているお客さんもあり。どん底の悲しみを味わえました。
ここで仲いりで、ほっ。
お仲入り
○口上
幕が開く。左から紅葉さん、紅先生、陽司さん
一門発足の披露目となりました。お弟子さんが増えて益々発展してほしいものです。
○桧山うめ吉 俗曲
日本髪が鮮やかなうめ吉さんの登場です。高座が華やかになる。
すととん節、木更津、おてもやん・・・唄と三味線が続く。
ぶらぶら節はやらなかった
最後はやっこさんを舞う。
○神田紅 立体講談 紅蓮源氏物語〜光源氏誕生
十二単姿の紅さんの登場です。これは紫式部なのでしょう。
早変わりで白い着物に袴姿。紅さんは今度は光源氏に扮して登場です。
猿之助歌舞伎のようです。
最後に早変わりで、また紫式部の姿に戻る。
歌あり、踊りありの楽しい芝居講談でした。
終演後、出演者スタッフが舞台に揃って、紅さんの締めのご挨拶。
そして紅一門はさっと抜けて、ロビーへ回る。
幕が閉じる時に中央にいたのはうめ吉さん。
お辞儀をしている姿で幕が閉じた。
ここだけ見たら、うめ吉さんの独演会だぞ。
|
|
|
| 2002.04.13 本牧亭講談定席 in お江戸両国亭 |
|
|
本日の本牧亭定席(でも両国亭)へ行って参りました。
行けなかった方々の為にちょっとだけ
早めに両国へ到着したので、公園で日向ぼっこをしながら昼食をとり、吉良邸へ向かった。八重桜が満開できれいだった。
両国亭へ到着してみると、入り口横に大きな「神田陽司」の看板。今週は「二つ目の挑戦」と題して、来年真打昇進が内定している陽司さんと明日は陽之助さんがトリを取るのです。
12時半。両国亭前。北陽さんは携帯とにらめっこ。陽司さんはコン
ビニバックを持って出たり入ったり落ち着かない。
木戸を入ると....
○神田紅葉 五郎政宗
今、これ勉強してるのね。
○神田きらり 山ノ内一豊 出世の馬揃え
も〜〜ミニ松鯉なんだから
○神田京子 巴御前の働き
北陽さんとおそろいのメガネをかけて登場です。(という私もお揃い
のメガネ...)
「今、前座は、五郎政宗ブームです。私もこの前の若葉会で勉強しま
したぁ」三人とも五郎政宗勉強中らしいです。はい
○神田北陽 谷風の情け相撲
両国といえば、らいおん堂で最小サイズのデカパンがお気に入りだそ
うです。
○神田茜 牡丹灯篭〜御札張り
「円朝作、茜脚色....」
春からオバケ根多でした。
オバケの「おつゆちゃん」主人公のラブコメになってました。
○神田愛山 甲州遊侠伝
清水次郎長のライバルを主人公にした結城昌治先生の作品を口演。
仲入り
○神田紅 源氏物語〜光源氏誕生
20日の独演会で読む根多の一つを披露。たぶん独演会へ来れないお
客様へのサービスも兼ねていたかもしれません。
○神田陽司 伊勢屋多吉
陽司さんは、オリジナルの新作(ご本人は今日の作品を新作古典と呼んでいます)を口演しました。
上がった時はあがり気味でしたが、だんだんと何時ものペースになる。
僕の好きな演者が揃って最高の寄席でしたが、拍手が非常にうるさかっ
たのが残念でした。
|
|
|
| 2002.04.06 ミックス寄席 |
|
|
浅草は木馬亭へやって来ました。「木馬名人会」と題して会へ行ってきました。夕方から気温が下がり、薄着だったので寒さとの戦いでもありました。
○柳家ごん白 落語 牛ほめ
先ずは前座さん。師匠ゆずりの与太郎がよかった。
○柳家三太楼 落語
明治時代、初めて電話が入って来た頃の噺。初めて聞く噺だった。
昨年秋、真打に昇進した三太楼さん、明日が最後の尋目を故郷でやるそうです。
○古今亭菊朗 落語 紙入れ
浮気噺。年増の女将さんの色っぽさがたまらないです。(師匠ユズリか)若いのに上手ですね。
○昔昔亭桃太郎 落語
出演者6人中、唯一芸術協会からの参加となった。3月31に行われた三派合同新作サミットでも9人中(色物さんは除いて)芸術協会は2人。内一人は講談の北陽さんなので、噺家では一人。寂しいなぁ・・・というマクラ。確かに新作の芸術協会と呼ばれていただけに、寂しい。
根多の方は、お馴染みのニュース解説、お見合いの噺の二本立て。野球に例えると内野安打的な笑いで、これが好きな人が多かった。ツウの集まるミックス寄席しかも名人会に呼ばれるだけのことはあります。
お仲入り
○三遊亭白鳥 落語 インド人のそば屋(仮称)
出囃子は「白鳥の湖」。何時から替わったのか、今日初めて気がついた。
着物の胸のキューピーちゃんのアップリケがカワイイ。
田舎をバカにするマクラから、根多に入る。
昼になった。あっさりした日本そばを食べようと、店を探すする主人公。そこへ客引きの謎の印度人が登場。しかもその印度人は、自分は日本そば屋の主人だと言う・・・
わりと大人し目なギャグばかりだった。新作の会ではないので、古典を聴きに来たお客さんへの配慮だったのかもしれません。
○柳家権太楼 落語 佃祭り
浅草演芸場の読売招待客へのグチ話し等のマクラをやり、根多に入る。
師匠のこの根多は初めて。前半部分をタップリ目。帰って来てからをトントンとやる。
与太郎の悲しむ場面は、間違いだと分かっていても涙がでてきた。与太郎が上手い!。
たっぷり笑って、スッキリして帰路に着いた。 |
|
|
| 2002.04.02 末廣亭4月上席(真打昇進披露興行
林家彦いち師匠の部) |
|
|
今席は、落語協会からの新真打5名の披露興行です。
第二日目は林家彦いち君。落語ジャンクション、落語21等でお馴染みの新作派。柔道2段、空手5段という肉体派落語家である。その披露興行の様子を覗いてみましょう。
今日は出演者が多いので一人10〜12分位の持ち時間。
○柳家小たか 落語
5時15分前。開口一番。お客さんは未だぽつりぽつり。
○柳家権太楼 落語 つる
いきなりの権太楼師匠登場でビックリ。
さっとやって、ひっこむ。 でも可笑しい。
○古今亭志ん太 落語 元犬
○綾小路きみまろ 漫談
ピンクのタキシードで登場。
一言多いのがウリの漫談。お客をいじって笑いをとる。
○入船亭扇治 落語 道具屋
噺家を絵に描いたような顔をした扇治師匠。与太郎噺をやる。
○松旭斎菊代 奇術
トランプの手品洋品を貰う。うれしい!!
早速練習。
○柳家さん吉 落語
○川柳川柳 落語
一昨日の新作サミットと同じ根多。「ガーコン」を聴きたかった。
○翁家勝乃ー之助/勝丸 太神楽
傘の曲を中心にさっとやる。
○桂文生 落語 ガマの油売り
久々に聴きました。口上は講釈師の方が上手と思います。
酔っぱらってからの口演が良かった。
○入船亭扇橋 落語
○三遊亭小円歌 俗曲
小円歌姉さんいいすよね。
最後の踊り「やっこさん」に目のやり場に困る。
○鈴々舎馬風 落語
お馴染みの漫談絶好調。
お仲入り
○真打披露口上
幕が上がる。頭を下げている紋付袴姿の6人。
左から司会の扇橋師、圓菊師、新真打の彦いち師、師匠の木久蔵師、馬風師、円歌師。
ここで後ろ幕のご案内です。可愛らしい林(森かも知れませんが、林という事にしておきます)をイメージした意匠です。小学館ビーパルさん(アウトドアライフの雑誌)寄贈です。寄贈品をもう一つ紹介します。舞台上手前に格闘落語家まんまな品「キックミット」(空手やキックボクシングでキックを受けるミット)が夢枕貘先生からです。
馬風師の口上「空手が怖いから真打にした」と楽しいお言葉。
三本締めで極める。
○あしたひろし順子 漫才
○古今亭圓菊 落語 饅頭こわい
いつも綺麗に決めるね。好きな師匠の一人です。
○三遊亭円歌 落語
「中澤家の人々」のクスグリを入れた漫談を短くやる。
○林家木久蔵 落語
彦六師匠の物真似で、師を偲び彦いちにエールを送る。
○林家正楽 紙切り
こちらは林家でも紙切りです。リクエストで披露口上を切る。楽屋口から見た口上の場面木久蔵師と彦いち師良かったです。欲しかったな。
○林家彦いち 落語 おしゃべりママ(仮称)
「待ってました」の掛け声と拍手に迎えられての登場です。今一番困っていること、それは母校国士館が寄贈したいという後ろ幕。そういってサンプルを取り出し客生へ見せた。ライジングサンの意匠の下に国士の文字。会場は大受け。嬉しいけど尋目では使えない。アウトドア落語家と言われるまで、格闘落語家の出来るまで等の今まで高座でやってきたマクラを次々と披露した後根多に入った。
中学生の息子を持つ母親。掃除の最中子供部屋のベッドのしたからエロ本を見つけてパニックに陥る。そして色々な人に言いふらすことに・・・・・
一時の肉体派根多から、誰でも楽しめる根多作りに移行して、形になってきた師匠です。
これからが益々楽しみです。
|
|
|