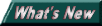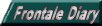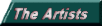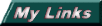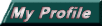| ◆寄席の基本◆ |
| 寄席 |
人を集めて芸能を催す「人寄せ場」の略。 江戸時代後期(1798年)、岡本万作という噺家によって、神田の藁店で興行したのが、常設寄席の始まりとされている。講釈や義太夫の寄席は早くから有ったはずだが、詳細は不明。
現在寄席とは、落語を中心にやっている場所をいうことが多い。
都内では浅草・浅草演芸場、上野・鈴本、池袋・池袋演芸場、新宿・末広亭の4大寄席に、国立演芸場を加えた5つが寄席とよばれている。
新しい寄席として、永谷の日本橋・お江戸日本橋亭、両国・お江戸両国亭、上野・お江戸上野広小路亭などが建つ。
1999年12月には、浅草演芸場の2階にフランス座東洋館という新たな寄席が出来たことは嬉しいかぎりである。しかし、東洋館に生まれ変わる前のフランス座にも1回は行って見たかった。
|
| 定席 |
毎日演ってる寄席。
尚講談だけをやる定席には、上野・本牧亭、浪曲の定席としては、浅草・木馬亭がある。
|
| 寄席の番組 |
寄席の番組は10日ごとに替わる。1日〜10日を上席(かみせき)と言い、11日〜20日を中席(なかせき)、21日〜31日を下席(しもせき)と言う。それぞれ出演者が変わる。また昼席(おおよそ12時〜17時00分頃まで)と夜席(おおよそ18時〜21時頃まで)の番組も違うものが組まれている。
|
| 木戸 |
切符売り場(テケツとも言う)とモギリの総称を、今でも木戸と言う。サッシだろうが自動ドアだろうが木戸という。
ここは、お客さんをチェックして楽屋に知らせると言う役割をする。たとえば、目の不自由なお客さんが来場した場合は、目に関係した噺をやらないようにとか。
入場料は木戸銭と言うが、これを略して木戸とも言う。
|
| 高座 |
寄席で芸人が演技をする場所を高座という。寺院で僧侶が説教するために一段高く設けた席を高座と言ったのが講釈(講談)の席に用いられ、やがて落語の席でも使われるようになった。
高座には、芸人の座る座布団(講談の場合はこれに尺台)と、名前をかける「めくり」があるだけのシンプルなインテリアで構成されている。
昔は鉄瓶をかけた火鉢も出されたようである。今は消防法の関係で、そういう風情も無くなったのだと思われます。
|
| 楽屋 |
高座の脇に芸人の控え室である楽屋と、お囃子さんがいる下座がある。 寄席によって場所や大きさは異なる。
|
| 座布団 |
座布団は袋状になっていて、4辺のうち、1辺にだけ縫い目がない、この辺が前に来るように敷く。
これは、人と人との縁が切れないようにとの縁起を担ぐため。という話しをマクラで聞いたことがある。
|
| メクリ |
高座の端に置かれる芸人の名前(何故か亭号は書かれない)が書かれた紙或いは札。メクリが出来てない前座さんは、「開口一番」のメクリが掲げられる。メクリはめくる為に在るのか、メクリ自身を見せるためにあるのかは、スカートの存在に似ている。
|
| 扇、手ぬぐい |
落語、講談、浪曲などの芸の区別なく使われる小道具。扇は箸、筆、刀、徳利、杯等、手ぬぐいは、半紙、財布、巾着、煙草入れ等の代わりとして、日本芸能にあるお約束記号として、作用する道具。お客さん側の想像力で何にでもなれる。
因みに楽屋用語では扇を「風」、手拭いを「曼陀羅」と言う。風とマンダラと続けて書くと、立川志加吾先生の週間モーニング連載中の4コマ漫画である。 |
| 招木(まねき) 招き看板 |
木戸口に主な出演者名を、その格に応じて書いて掲げた、表札大の看板。「お客様を寄席に招くように」との願いを込めて、寄席文字橘流一門から新真打に送られる。
|
| 毛氈(もうせん) |
| お仲入り |
| 山台 |
| お仲入り |
| うしろ幕 |
噺家の真打昇進披露や、襲名興行で、高座を彩る幕で、高座の後ろに張る。寸法は、横7m10cm,縦2m48cmとかなりでかい。デザインは様々。元来出世した時に贔屓のお客様から贈る物。
披露目が終わった後、この幕はどうするのだろう。
|
| 番組の流れ 進行/寄席の一日 |
○開演30分前
寄席は、開演30分程前、一番太鼓で始まる。テケツの横の櫓の上で、前座さんが「どんとこい、どんとこい」と叩く太鼓である。(上野鈴本の例)
○開始15分前
BGMを担当するミュージシャン(お囃子のお師匠さん達)や、トップバッターを勤める二ツ目さんが入ります。
○開演間もなく
2番太鼓が鳴ると、間もなく開演。
○開口一番(サラ口ともいう)
開演の一つ前に、前座さんの高座から始まります。講釈場の場合は、お客様が入る前の高座と言うことで、空板(からいた)と言います。この前座さんの高座を「空板と叩く」と言います。
こうして番組は始まっていくわけですが、番組の最初の方を浅い出番、終わりの方を深い出番と言います。
○仲入り
プログラムが進み、7〜8組の芸が終わる頃、時間も2時間程経過し、お客様の集中度も落ちた頃、「お仲入り」という休憩となります。この中入り直前の高座を「仲入り前」とか「中トリ」と言い、トリを取る人に準ずる人や、メインゲストが勤めます。この高座が終ると、「おな〜か〜いり〜」の声とともに幕が閉まりお仲入りとなるわけです。
トイレや軽い食事を済ませる十数分が経過すると、お囃子が始まり、幕が開き、後半が始まります。
○後半最初は
後半の出演者の数は少なく(後半というよりは、終盤と言った方が良いかもしれません)、最初の出番を「くいつき」と言い、休憩モードに入っていたお客さんを高座に集中させるインパクトのある芸も見せる人1〜2人がこの任に当たります。
○それから
「膝がわり」と言い、最後(トリ)の芸を引き立たせる重要な役で、色物の芸人さんがこの任にあたります。
○最後が
「トリ」と言い、主役・横綱・メインエベンター(死語)の芸人さん(今では主任と言います)が高座を勤めます。トリの芸人さんの噺が終わり、「ありがとうございます」のお辞儀をすると同時に、「ありがとう〜ござい〜ました〜」の声がして、幕が閉まりお開きとなります。
○追い出し太鼓
刹那、客様は、トリ根多の余韻に耽っている間も無く、「でてけ、でてけ」の追い出し太鼓の響きで現実世界に引き戻され、家路につくことになるのです。追い出し太鼓の最後は、カラカラカラ・・で終わる。
|